来る2006年2月26日、東京都北区の男女共同参画センターにおいて、政策形成における市民の参加についての講義と、政策立案のワークショップを行ってきました。
依頼を受けた内容は、
●なぜ調査し、学ぶのか
・参画−市民に求められる力
・政策の形成−市民にどのような機会があるのか
・なぜ、学ぶこと調べることが大切なのか
これらをワークショップをまじえて、おおまかな過程と学習することがこの講座の目的となりました。
<プログラムの概要>
1.「まちづくり」の時代がやってきた:市民の参加をめぐる状況(1)
2.市民が政策を作り提言する時代(背景・政策関与の事例):市民の参加をめぐる状況(2)
3.政策形成・決定・実施過程のサイクルと参加の仕組み
4.解決策を考える(男女共同参画の視点・事例をとおして)
5.政策をどのように実現するかを考える
6.調査・分析の方法について:説得力のある政策立案のために
7.市民の調査で心がけるべきこと
1.「まちづくり」の時代がやってきた:市民の参加をめぐる状況(1)
2.市民が政策を作り提言する時代(背景・政策関与の事例):市民の参加をめぐる状況(2)
1,2では、市民の参加の状況を、まず、「社会的・経済的背景と地方分権の動き」(1)から、そして、「国と地方の動き」(2)から説明させていただきました。
3.政策形成・決定・実施過程のサイクルと参加の仕組み
ここでは、見出しのタイトルのとおり、政策形成・決定・実施のサイクルについて説明したのち、そこに市民がどのように参加・協働をすることができるかについて、私なりの見解をお話しました。
4.解決策を考える(男女共同参画の視点・事例をとおして)
これまでのお話をふまえて、男女共同参画やジェンダーに関する統計データを読み、そこから政策立案のワークショップを行いました。手順の流れは以下の通りです。
|
(『シチズン・リテラシー』(教育出版)p.203を参照) | 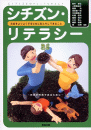 |
ACTION 政策案をつくってみよう
1.調査したことや意見をまとめよう
|
(1)調査したことやデータから社会課題や問題を抽出する
(2)問題の根元を考える
(3)みんなのビジョンをまとめよう:「どのような社会にしたいのか」を話し合おう
(4)実現にむけて障壁となっているものを考える
2.既存の政策を評価し、改善策を考えよう
3.実現したい政策案をまとめよう
4.検証してみよう
5.政策をどのように実現するかを考える
みなさんが作った政策案を発表し、これをどのようにすればよいかを話し合います。(今回は大まかな流れを説明するにとどまりました。)手順や考え方については、『シチズン・リテラシー』(教育出版)p.206をご参照下さい。
・国・地方の関係について
・政策立案・形成・実行過程のサイクル(各過程での参加事例)
・立法化・予算化・事業化
・その他の方法
など
6.調査・分析の方法について:説得力のある政策立案のために
ここまでのお話とワークショップで、調査や分析の位置づけが分かってきます。どこでどんな調査があるか、どんな効果があるかなどについてお話しました。
・どこで調査・分析が必要になるか
数字が政策を動かすことがある DV、出生率、ニート、ジニ係数など…
・どのような調査・分析の方法があるか:「見えないものを見る力」
7.市民の調査で心がけるべきこと
そして簡単に、調査のなかで心がけるべきことを説明しました。統計の処理などはとても難しいですが・・・。
<おわりに>
最後に、これからの関わり方について、いくつかお話しました。身近な取り組みや政治との関わりなど、さまざまな切り口から、「社会をよりよくするために私たちにできること」があり、それを考えることがシティズンシップなのだと思います。
(反省点など)
ワークショップは生ものなので、とても難しいです。2時間のなかでどれだけできるか心配でした。立案のワークショップが、2時間のなかで40分でした。最初の説明が1時間、発表が20分だったので、あと30分ほどあれば、最後のまとめができたのですが、私の時間の読みがまずかったのが、反省すべきところです。
言い訳としては、ERICの手法と、私たちの手法に違いがあり、まとめる手順などでは、そのあたりで噛み合わなかったところがありました。
●本ワークショップの成果物
| 
